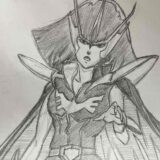今回はうつ病になってしまった場合に仕事・職場での状況はどうなるのかについてお話ししたいと思います。休職・退職・復職のメリットとデメリットを体験談から紹介します。再発防止のために必要な治療やキャリアプランについても解説します。
目次
大まかな流れ
まずは会社を休むところからはじまります。病院・クリニックの予約は取りづらいので早めに予約するようにしましょう。
≫ 健康に大ダメージ!本当に怖いうつ病あるある8選!(体験談)
 健康に大ダメージ!本当に怖いうつ病あるある8選!(体験談)
健康に大ダメージ!本当に怖いうつ病あるある8選!(体験談)
ここからが今回の記事内容です。
会社に休職制度があるかどうかがポイントです。就業規則を確認してみましょう。ある場合は休職、ない場合は退職になります。
休職期間中に症状が回復すれば産業医の面談を経て復職となりますが、回復しなければ退職となります。
自分の体調が第一です。くれぐれも休職期間に合わせて無理して復帰しないようにしましょう。
復職した場合は、産業医・職場の上司と面談ののち決めた通り、軽い業務から再開することになります。
一度うつ病になってしまうと、元の体調に戻るのは難しいです。少なくとも同じ働き方はできないでしょう。新しく自分に合った働き方を見つけることが重要です。
多くの場合は軽い負荷の部署に異動になるか退職・転職することになります。新しい自分に適応するのはそれだけ難しいのです。
無理せず自分に合った働き方ができる職場を選びましょう。
大きく分岐するのが、うつ病と診断された後と休職期間が満了した時だと思いますので、分岐ごとの対応についてお話ししていきたいと思います。
うつ病とは何か
うつ病とは、精神的ストレスや身体的ストレスなどが重なり、強いうつ状態が長く続くことで日常生活に支障が出る精神障害(精神疾患)の一種であり、様々な理由から脳の機能障害が起きている状態のことを言います。
厚生労働省の調査では100人に6人が経験する病気であり、決して珍しい病気ではないことが報告されています。
日本では、100人に約6人が生涯のうちにうつ病を経験しているという調査結果があります。また、女性の方が男性よりも1.6倍くらい多いことが知られています。女性では、ライフステージに応じて、妊娠や出産、更年期と関連の深いうつ状態やうつ病などに注意が必要となります。
厚生労働省:みんなのメンタルヘルス
うつ病の主な症状は以下のようなものです。
- 憂うつな気分や意欲の低下
- 睡眠障害や食欲不振
- 自己否定感や罪悪感
- 集中力や記憶力の低下
- 自殺念慮や自傷行為
これらの症状は個人差があり、重度によっても異なります。また、季節や時間帯によっても変化することがあります。
仕事は人生における大きな責任と役割です。しかし、うつ病になると仕事をすることが困難になります。その理由は以下のようなものです。
- 仕事への興味やモチベーションが失われる
- 仕事量や期限に対して過剰に不安を感じる
- 上司や同僚とコミュニケーションを取ることが苦手になる
- ミスやトラブルを起こしやすくなる
- 休みたくても休めない罪悪感や周囲への配慮から無理をする
これらのことから、うつ病で仕事をすることは非常にストレスフルであり、体調や心境をさらに悪化させる可能性があります。
休職制度がある会社の場合
会社に休職制度がある場合は休職制度を利用しましょう。期間は会社によってまちまちですので、就業規則か人事に確認してみましょう。数ヶ月のところもあれば1年以上の休職が可能な企業もあります。
うつ病(精神疾患)になってしまった場合は、回復するまで6ヶ月以上かかることを考えた方が良いので、場合によっては休職期間が満了して退職するということも考えておく必要があります。
もし、あなたが休職制度がある会社で働いていて、うつ病で仕事が辛い場合は、休職制度を利用して治療に専念することをおすすめします。私自身も以前勤めていた会社で休職制度を利用して3ヶ月間治療した経験があります。
- 仕事から解放されて療養に専念できる
- 医師やカウンセラーと定期的に面談して治療計画を立てられる
- 薬物治療だけでなく心理教育や認知行動療法などの心理療法を受けられる
- 会社から給与や社会保険などの支給が継続される
- 休職期間中に仕事のスキルや知識が低下する可能性がある
- 復職後に仕事に適応できるか不安になる可能性がある
- 上司や同僚との関係が変わってしまう可能性がある
- 休職期間中に自分を責めたり孤立したりする可能性がある
- 医師から診断書をもらって会社に提出すること
- 休職期間や復職条件などを会社と明確に確認すること
- 定期的に医師やカウンセラーと連絡を取り、治療計画を見直すこと
- 家族や友人など信頼できる人とコミュニケーションを取り、支え合うこと
もし長時間労働や、上司のパワハラ・セクハラ等が精神的負担の原因と考えら得る場合は、労災申請も検討しましょう。
休職制度がない会社の場合
もし、あなたが休職制度がない会社で働いていて、うつ病で仕事が辛い場合は退職して治療に専念せざるを得ない場合もあります。休職制度は義務ではないため、就業規則に記載されていない場合はよく確認しておいた方が良いかもしれません。
その場合は自動的に退職となってしまいますので、就業規則をよく確認しておきましょう。
もしその場合、退職したくないからといって、無理に仕事を続けることは絶対に避けてください。うつ病はなったことがない人が理解できるほど簡単な病気ではありません。
想像以上に回復までの期間が長引くか、最悪の場合はずっと治らず、復帰して休んでを繰り返すことになります。実際に私の周りにも復帰して休んでを繰り返す状態の人がいましたので、軽く考えないようにしましょう。
- 仕事から解放されて心身共に回復する時間が得られる
- 医師やカウンセラーと定期的に面談して治療計画を立てられる
- 薬物治療だけでなく心理教育や認知行動療法などの心理療法を受けられる
- 次のキャリアプランをじっくり考えられる
- 会社から給与や社会保険などの支給が途切れる
- 次の仕事を探すことが困難になる可能性がある
- 上司や同僚との関係が断絶してしまう可能性がある
- 退職したことに対する自己否定感や罪悪感を抱く可能性がある
- 医師から診断書をもらって会社に提出すること
- 退職時期や退職金などを会社と明確に確認すること
- 治療費や生活費などの資金計画を立てること
- 家族や友人など信頼できる人とコミュニケーションを取り、支え合うこと
休職期間が満了したとき


休職期間が満了するときに体調が回復してる場合は晴れて職場復帰となります※くれぐれも休職期間の期限が迫っているからと言って無理に復帰してはいけません。すぐにまた体調不良となり治療期間が長引くことになります!。
いきなり従来の業務をそのまま再開するのはハードルが高いでしょうから、上司や部署の方達と話をして、業務の配分が行われると思います。そこで徐々に業務に慣らしていき、業務に耐えられる耐性を作っていきます。
再発防止策は以下のようなものです 。
- 医師や産業医と定期的に面談して治療計画を見直すこと
- 薬物治療だけでなく心理教育や認知行動療法などの心理療法を受け続けること
- ストレス管理やリラックス法などの自己ケア方法を学ぶこと
- 仕事量や期限などのワークライフバランスを整えること
- 上司や同僚などの周囲への相談・協力・サポート体制を作ること
休職期間満了で退職される方も少なくないと思います。
その場合は継続して傷病手当金もしくは労災の休業補償を受け取ることで生活することになります。
もし、どちらももらえていない場合は必ず申請しておきましょう。
特に労災申請は補償が手厚いので、認定のハードルは高いですが、原因が職場にあると考えられる場合は検討してみるのもいいでしょう。
私は労災の補償に大変助けられていますので、申請をしてみる価値はあると思います。
労災とならずに残念ながら退職となってしまった場合には、傷病手当金を継続して受け取れるように、受け取り条件をよく確認しておきましょう(最長で1年6ヶ月受け取ることができます)。
注意しておくべきなのは、退職後に傷病手当金が受け取れる条件は保健組合に1年以上加入している人、つまり1年以上その会社で勤めている人となりますので注意してください。
再発しない様に仕事をする


復帰してからは、上司や産業医と話をしながら仕事を再開することになります。
最初は簡単な仕事から始め、徐々に業務の負荷を上げていくことになります。
注意しなければならないのは、ここで無理をして負荷を上げすぎてしまうということです。
参考までに記載しますが、うつ病の再発率は60%を超えます(厚生労働省調べ)。
再発するたびに再発率は上がっていくため、慎重に自分の体と対話しながら仕事をしましょう。
キャリアアップを目指していた方は一歩立ち止まることが必要となりますが、焦らずに頑張りすぎないようにすることが必要です(従来の自分とは違う自分であることを受け入れる必要があります)。
部署異動もしくは転職


職場復帰を果たしたとしても従来通りに働けないというのが現実です。
会社側もそれは分かっているので、大抵の場合は業務負荷の少ない部署への異動というケースが少なくありません(クビにはできないので)。
そのため、復帰後に結局退職・転職して新天地での再スタートを図る方も珍しくありません。
現在働いている会社での立場を考えて今後のキャリアを検討することになると思います。
フォローしてくれる会社であれば、一緒に頑張っていくのもいいでしょうが、役立たずとして閑職に追いやられるのであればそこまでの会社であるということを割り切る必要もあると思います。
実際のところ、うつ病の理解というのは社会で騒がれているほど進んでいないというのが私自身感じました。
心無い言葉をかけられることもあると思いますが、その場合は転職も視野に入れるのが良いでしょう。
今のあなたに合った職場というのがあるはずですので、そこを探すのが現実的だと思います。
会社が原因精神疾患になった場合は、会社を訴えることも検討しておきましょう。
うつ病は長く、金銭的にも苦しくなる病気です。会社に原因があるなら損害賠償請求が可能な場合もあります。
参考|弁護士西川暢春の咲くや企業法務TV
まとめ
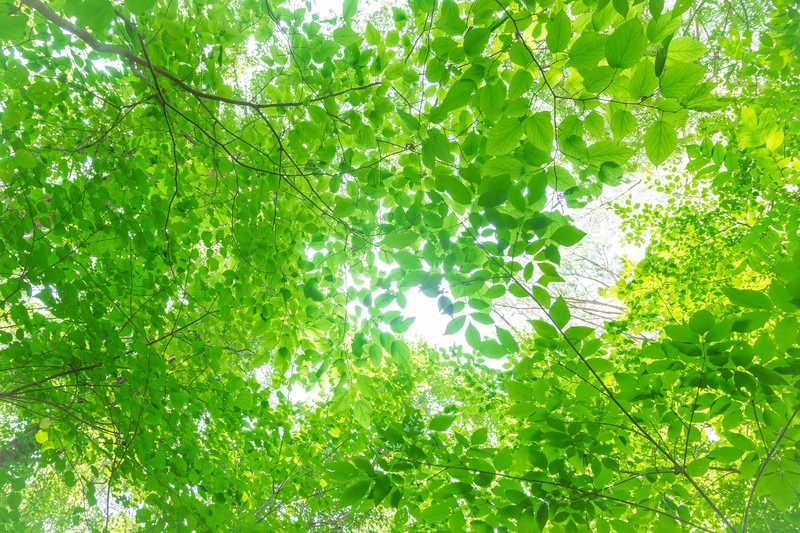
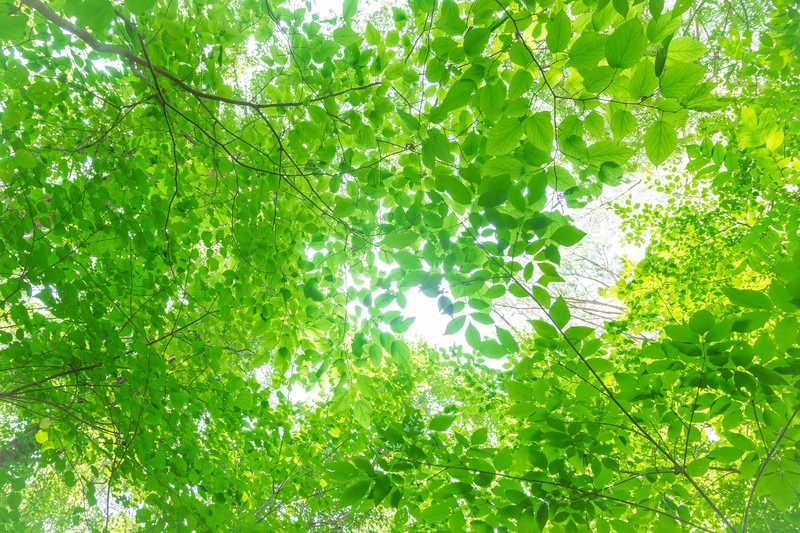
以上、うつ病になってから復帰までの道のりを見てきましたが、いくつも壁が存在することがわかります。
以前と同じように働けない自分とどのように付き合っていくか。
職場にの人間たちが自分を見る目がどのように変わっていくのか。
会社からの評価はどのように変化したのか。
いずれにしてもしっかりと働けるようになるまでには時間と労力が必要になるので、長い時間付き合っていく必要があります。
焦らずに、自分のペースを守ることを優先すべきだと思いますので、業務を行うのが今の自分にとって無理をすることが必要なら、退職して回復に努めるか、転職してもっとストレスの少ない職場を探すなどの選択肢を持っておくことが重要だと思います。
以上、今回はうつ病などの精神疾患になってしまった方が直面するであろう事態について書きました。
正直しんどい状況が続くと思いますが、まずは受け入れるところから始め、一歩ずつ前進していきましょう。
この記事がお役に立てれば幸いです。
それでは