あなたは会社から「管理職」として扱われていますか?もしそうなら、残業代はもらえていますか?
実は、管理職という肩書きだけで残業代を支払わない会社は違法です。管理監督者として認められるには、一定の条件があります。その条件を満たさない場合、あなたは「名ばかり管理職」と呼ばれる存在であり、残業代を請求する権利があります。
しかし、名ばかり管理職の残業代請求は簡単ではありません。会社側は責任を認めずに抵抗することが多く、労働基準監督署に相談しても解決しないことがあります。
そこでおすすめするのが、弁護士に依頼する方法です。弁護士に依頼すれば、労基署よりも早く確実に残業代を回収できます。この記事では、弁護士に依頼するメリットと流れを詳しく解説します。
別記事でも紹介しましたが、労働基準監督署の調査には法的強制力がないため、会社側は拒否しようとすれば拒否できるのです。
全体の流れを整理すると下記のようになります。
①|勤怠記録(メモでも可)②|給与明細 ③|雇用契約書 ④|就業規則 ⑤|賃金規定 ⑥|組織図| ⑦|上司からの指示記録(メールでもメモでも可)
 残業代請求で成功したい人必見!証拠集めから交渉までのコツと注意点
残業代請求で成功したい人必見!証拠集めから交渉までのコツと注意点
弁護士に状況説明し契約
交渉がまとまれば和解。場合によっては裁判の可能性もある
弁護士を通じて残業代の金額が振り込まれる
全体の流れについては次の記事で詳しく記載しています。



全体像を確認するとこのような流れになります。労働基準監督署を使う場合はSTEP1とSTEP2の間に労働基準監督署の手続きが入ります。
私の場合は労働基準監督署への依頼を含めて手続きをしましたが、全部で6ヶ月ほどかかりました。労働基準監督署だけだと1ヶ月ほどなので、最初から弁護士に依頼しておけば5ヶ月程度だったと思います。
担当弁護士の話では、通常の残業代請求の場合は6〜10ヶ月程度とのことなので、それなりに時間がかかると思った方が良いと思います。
目次
労働基準監督署より弁護士を選ぶ理由
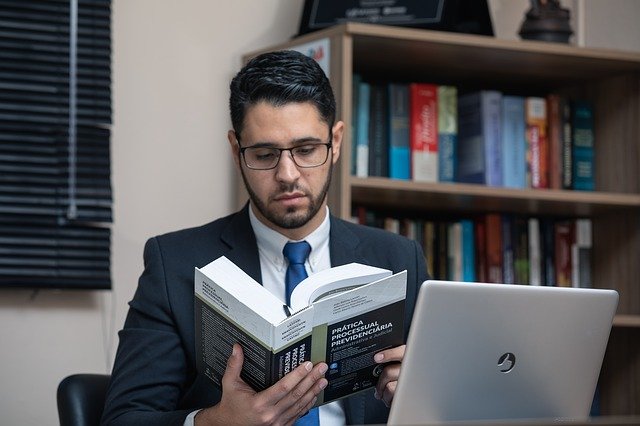
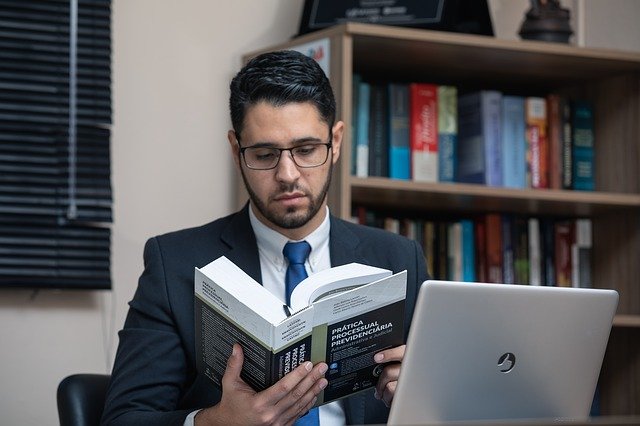
名ばかり管理職の残業代請求を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 労基署よりも早く回収できる
- 交渉力が高い
労基署に相談した場合、まずは調査や指導を行います。しかし、これらの手続きには時間がかかる上に、会社側が応じない場合もあります。その場合、裁判所へ提訴する必要がありますが、改めて弁護士を探してから依頼するという手続きを踏まなければなりません。
一方、弁護士に依頼した場合、最初から裁判所へ提訴することが可能です。労働基準監督署に対し、弁護士の場合は裁判まで持っていくことができますから、会社の立場からすると無下にはできません。
会社側が無知という可能性もありますが、大抵の場合は顧問弁護士がついているため、法的なやりとりに焦点を当てることができます。
会社側からすれば、裁判費用だけでなく、世間の評判や未払い残業代を支払った場合の金額などを考えると早期解決に動く場合が多いと考えられます。
名ばかり管理職の残業代請求は、会社との交渉が重要です。会社側は、管理職であることを主張したり、残業時間を否定したり、和解金額を低く抑えようとしたりします。
しかし、弁護士に依頼すれば、これらの交渉を有利に進めることができます。弁護士は、法律や裁判例に基づいてあなたの立場を主張し、適正な残業代を算出し、最大限の和解金額を目指します。
また、弁護士が介入することで、会社側も真剣に対応せざるを得ません。会社側は、裁判になると負ける可能性が高いことや、裁判費用や時間がかかることを恐れています。そのため、弁護士からの交渉に応じて和解するケースが多いです。
実際私が弁護士を利用した時もすぐに会社側は和解交渉を提案してきました。
名ばかり管理職の残業代請求を弁護士に依頼する方法
名ばかり管理職の残業代請求を弁護士に依頼する方法は、以下の通りです。
まずは、名ばかり管理職の残業代請求に詳しい弁護士を探す必要があります。弁護士は、専門分野や経験などによって得意不得意があります。そのため、労働問題や残業代請求に慣れている弁護士を選ぶことが大切です1。
弁護士を探す方法としては、以下のようなものがあります。
- インターネットで検索する
- 口コミや紹介で探す
- 法律相談所や法テラスなどで紹介してもらう
インターネットで検索する場合は、「名ばかり管理職 残業代 請求 弁護士」などのキーワードで検索してみましょう。また、口コミや紹介で探す場合は、「実際に依頼したことがある人」や「信頼できる人」から情報を得ることが重要です。
法律相談所や法テラスなどでは、無料または低額で法律相談が受けられたり、適切な弁護士を紹介してもらえたりします。しかし、これらの機関では、「予約制」だったり、「時間制限」があったり、「希望する弁護士とマッチングしない」可能性もあります。
そのため、自分でインターネットや口コミなどで調べてみることもおすすめです。ただし、インターネットや口コミだけでは判断しづらい場合もあります。その場合は、「無料相談」を利用してみることが有効です。
※参考までに、私が弁護士を探すのに利用した日本労働弁護団をご紹介します。この弁護団は労使関係に強い弁護団で、全国に支部があり、電話相談も可能です。
多くの弁護士事務所では、「無料相談」というサービスを提供しています。「無料相談」とは、「初回だけ」「一定時間だけ」「無料で」「法律相談が受けられる」というサービスです。
「無料相談」では、以下のような内容を話したり聞いたりすることができます。
- 自分の状況や問題点
- 弁護士の経歴や実績
- 残業代請求の見込みや方法
- 弁護士費用や支払い方法
「無料相談」では、「自分に合った弁護士かどうか」「信頼できる弁護士かどうか」「依頼したい弁護士かどうか」などを判断することができます。
また「無料相談」では「依頼しなくても良い」という選択肢もあります。
「無料相談」を受けるには、弁護士事務所のホームページや電話などで予約をする必要があります。予約時には、「名ばかり管理職の残業代請求について相談したい」という旨を伝えましょう。
また「無料相談」に行く前には、以下のような準備をしておくと良いでしょう。
- 職務内容や役職名などの自分の立場を明確にする
- 残業時間や残業代の支払い状況などの証拠となる書類やデータを持っていく
- 弁護士費用や支払い方法などに関する質問を用意する
「無料相談」で弁護士と信頼関係が築けたら、次は弁護士と契約することになります。「弁護士と契約する」とは、「弁護士に依頼して、残業代請求の手続きを任せる」ということです。
弁護士と契約する際には、以下のような点に注意しましょう。
- 契約内容や条件を書面で確認する
- 弁護士費用や支払い方法を明確にする
- 連絡方法や報告頻度などを決める
- 依頼内容や目的を共有する
弁護士と契約したら、あとは弁護士が残業代請求の手続きを進めてくれます。ただし、進捗状況や必要書類などは定期的に報告してもらうようにしましょう。
最後に、残業代請求の結果を受け取ることになります。残業代請求の結果は、以下のようなものがあります。
- 和解:会社側が一部または全額支払うことで合意した場合
- 裁判:会社側が支払い拒否した場合で、裁判所が判決した場合
- 不成立:会社側が倒産したり、証拠不十分だったりした場合
和解や裁判で成功した場合は、会社から残業代が支払われます。ただし、和解金額や裁判費用などから弁護士費用が差し引かれることもあります。そのため、実際に手元に入る金額は事前に確認しておきましょう。
私の場合は退職後に残業代請求を行ったため、人間関係など会社との関係を気にする必要はありませんでしたが、在職中の場合、残業代請求の結果によっては、会社との関係が悪化したり、解雇されたりするリスクもあります。そのため、弁護士と相談しながら、自分の状況や目的に合った方法を選ぶことが大切です。
以上が、名ばかり管理職の残業代請求に弁護士を依頼する方法の例です。この例はあくまで一般的な流れであり、個別の事情によって異なる場合もあります。実際に残業代請求をする場合は、必ず弁護士に相談してください。
裁判になる可能性は?


裁判に入る前の和解交渉がメインの流れとなるでしょう。
ただし、金額が大きかったり、相応しい権限が与えられている場合など、争う価値があると会社が判断した場合は裁判となる可能性もあります。
私の場合は、裁判に行かずに和解という結果になりましたが、ほぼこちらの請求額通りに支払いが行われました。
労働基準監督署を使うメリットは?


労働基準監督署には金銭的な負担がないというメリットがあります。そのため、時間的余裕がある場合は試してみるのもいいかもしれません(実際私はやってみました)。一方、法的強制力を持たないために会社側が支払いに応じない場合があります。
反面、弁護士の場合は弁護士費用がかかるというデメリットがありますが、裁判を見越したプレッシャーを企業にかけることができるので、早期解決につながりやすいです。
厳密には、労働基準監督署の調査と弁護士への依頼の間に「労働審判」という手続きがありますが、早期解決を目指した法的手続きではあるものの、自身で交渉しなければならない点でハードルが高いという点。また、企業側に足元をみられ、金銭的な譲歩をせまられる場合が多く(弁護士談)、結局弁護士に依頼するという流れになるとのことなので、最初から弁護士に依頼したほうが結果的に早く解決に進むでしょう。
まとめ


私も最初はどの手続きが効果的なのか迷い、最初は労働基準監督署に依頼をしましたが、結果を見ると最初から弁護士に依頼したほうが楽でした。
弁護士と聞くと身構えてしまう方は多いかもしれません。
かくいう私も弁護士への依頼というと、「なにかとんでもなく大変なことをしなければならない」という感情になりました。
ですが、弁護士はもっと身近なものです。
感覚的には「ネットの回線工事」への申し込みくらい身近です。法律とはそれくらい身近なものなのです。
もちろん相談料や弁護士報酬などはかかりますが、弁護士にしかない強制力というのは大きな武器となります。
残業代請求に限ったことではありませんが、トラブルの時に泣き寝入りする機会を減らすことができるので、つながりや連絡方法を持っておくことが大事です。
念のため、法律関係で頼るべき場所を載せておきます。
法律関連全般|法テラス
労使関係|日本労働弁護団
この2つを覚えておくだけでも、万が一の時に対応することができます。
以上、今回の記事がみなさんのお役に立てれば幸いです。
それでは





